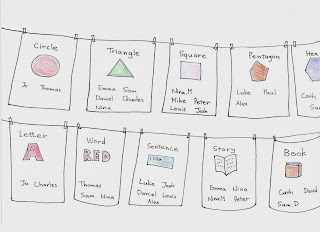日本のディスレクシア
息子が英国へ引っ越す時に、 息子と仲良くしてくれた近所の上級生のお父さんが 「引っ越しちゃうと漢字を読んでくる人がいなくなって困っちゃうね。」 とつぶやきました。
なんのこと?と首をかしげる私。
小学校1年から不登校生の息子でしたが、なぜか漢字を読むのだけは好きでした。 息子の興味のあることに気がついた校長先生は、校長室での個人授業でも漢字を取り上げてくれました。ひらがなを書くのも億劫な息子ですが、なぜか漢字を読むのは得意になりました。
不登校生の息子に声をかけてくれて一緒によく遊んでいた上級生のお友達。誘われてはその子の家に行って、一緒にコンピューターゲームをした息子。
漢字が苦手なその上級生はゲームをしている時漢字が出てくると息子に読んでもらっていたとその子のお父さんが教えてくてました。
初めて知った事実。不登校生でまともに勉強できずに学力が遅れている息子。
たった一つの得意なことがこんなところで活躍していたなんて。
不登校生でも誰かの役に立つことができるんだ。
心に奥がポッと暖かくなった一瞬でした。
中学校に進学したこの上級生がディスレクシアだったと知ったのはその後でした。
イギリスではよく聞く「ディスレクシア(dyslexia)」という言葉。
日本で聞いたのは、この友達が初めてでした。
日本語でもディスレクシアってあるんだぁ。
ディスレクシアは聞いた言葉の綴りを書くことができない学習障害。
初めて耳にしたのはイギリスでした。
イギリスのディスレクシア支援体制
電話先の仕事相手に「今の言葉のスペルを教えて。」と聞いた時。
「僕はディスレクシアだから教えられないんだよ。電話では自分の名前のスペルを教えることもできない。」と言われてびっくりしました。
電話先の相手はロンドンの有名芸術大学院を卒業した現代作家。一緒に仕事をしていても頭のいい彼の学力を一瞬も疑ったことはありませんでした。読書も好きな彼はいつも本を手に持っていました。
とっても難しい本を読んだり哲学的なことを考えたりできるのに、自分の名前も書くことができないなんて、そんなことがあるの? それがディスレクシアとの出会いでした。
彼の高校は有名人を卒業生に多く持つ私立学校。2012年のロンドンオリンピッックでは、金賞受賞者2名を含めた8名の受賞選手を出しました。「僕の通っていたミルフィールド(Millfield)はディスレクシアのサポートが充実しているんだよ。」
 |
| Millfield School (photo:テレグラフ紙) |
 |
| 2012年のオリンピックでは卒業生が活躍 (photo:the Daily Mirror) |
ディスレクシアのレベルは個人差がありますが、イギリスでは学校や大学あるいは多くの資格コースでもサポート体制があります。ディスレクシアだから進学できない、資格が取れないということはありません。
義理の姉が二人目を産んだ後に何を思ったか法廷弁護士の資格BPTCを取る為に、大学院へ入学。ディスレクシアの受験生はコンピュータを利用して資格試験を受けれます。ディスレクシアと認められた彼女でも無事卒業試験にも合格。
「単語の綴りが書けないからといって、個人の学力や知能力に限りがあるのとは違う。
少しの支援があれば個人の可能な限りの能力が発揮できる。」
そして、「それを認めよう。」という考えでしょう。
英語のディスレクシアに日本語教育がいい。
英語は発音と単語のスペルの関係が複雑です。26文字のアルファベットの組み合わせで40以上の発音があります。ディスレクシアは英語ならではの学習障害だと思っていました。文字の発音と字が一致する日本語ではディスレクシアはないと思っていた私。不登校生の息子が独力で辞書や図鑑を読み進めていけるのは、この日本語の特性のお陰と思っていました。
でも、漢字があったのね。
確かにひらがなやカタカナは発音通りの綴りですが、漢字はいくつも発音があるし、発音と綴りの関係が複雑です。漢字と英語の単語はそういう意味で似ているかな。
漢字のディスレクシアで困っている日本のお友達。でも、アメリカやイギリスの学校では英語のディスレクシアの生徒に日本語や中国語を習わせると習得がよいという結果が出ています。英語だとスペルが書けないけど、日本語だと作文が書けるようになったというアメリカのディスレクシアの13歳。イギリスの学校ではディスレクシアの生徒の為に日本語の授業を行っています。
ディスレクシアの認知度
最近になってディスレクシア教育の体制が整ってきたイギリスですが、義理の母曰く娘がディスレクシアとは大学院へ行くまで知らなかった。
「そういえば昔から学校の宿題で同じ言葉を3回違うスペルで書いていたけど。。。ディスレクシアなんて言葉も知らなかった。」
イギリスでもディスレクシアという言葉が普及していなかった時があったのですね。
日本ではまだまだ聞き慣れないこの言葉。 ディスレクシアと判定されても通っていた中学校ではディスレクシアと認めてもらえかった息子のお友達。
漢字が読めないのにどうやって入試試験を受けれるのだろうか。学校で認知があれば入試の際のサポートもあるのに。。。不安を抱えながら通える高校を探すご両親。不登校生の息子にもあう学校があるのではとあちらこちらへと足を運んだ昔の自分と重なります。
漢字は苦手でもひらがなやカタカナはすごい速さで読むことができます。
社交的でスポーツも得意なお友達。
中学校のスポーツ部でも活躍して、高校は得意なスポーツでの入学が決まりました。
彼の才能を見分けた中学校の先生が推薦してくれました。推薦試験に無事に合格。
高校入試時期を待たず一足先に進学先が決まりました。
ご両親も予想していなかった結果。
得意なことがあれば必ず誰か見ていてくれるのね。
高校入学おめでとう。
できないことより得意なことに目を向けて元気に歩いていければきっとどこかへつながるのね。
ランキングに参加しています。よかったらご協力ください。
関連する記事
英国の特別支援 イギリスの小学校
参照 Dyslexics excel at Japanese, The Guardian, 2006
Unlocking Dyslexia in Japanese, the Wall Street Journal, 2011
London 2012 Olympics: The private school that produced eight of the Olympians,The Telegraph,2012
The Amazing Wilson: Schools' Cup final blow drove Peter to Olympic glory, The Daily Mail, 2012